054.やられても、やり返しません
- にじこさんからの相談 5歳9ケ月の男の子
-
長男のことでご相談です。幼稚園では「強い子(わんぱく)」たちにいろいろ言われたりしているようです。キックされたり、叩かれたりしても逃げることが多いので、おもしろがって、なおさらされるみたいです。
先日は、幼稚園で親子参加の交通安全教室がありました。みんなの前で「○○(長男の名前)、負けろ。○○、負けろ」と合唱されてしまい、私は唖然としました。担任の先生に相談すると、「○○くんは、穏やかでとてもやさしい子。幼稚園はこんな子どもを育てようとしている。 ○○くんのことをみんなが認め、みんなでお互いを認め合うようなクラスにしたい」とおっしゃいました。
それを聞いて涙がでてしまったのですが、先生がおっしゃるには、これまでの年少・年中の2年間で、このような力関係ができあがってしまっているとのことでした。
年少の入園時に、私が「叩かれても、叩き返したらだめだよ。暴力はいけないよ」と言い続けてきたせいか、仕返しもほとんどしません。今思えば、そんなこと言わなければよかったのかもしれませんね。祖母が幼稚園の先生だったもので、その影響もあります。
また、強い子が、息子が使っているコマを「貸して」と言って「これは○○が使っているから、自分のもってきたら?」と言われるやいなや、そのコマを踏んづけるという意地悪なところも目撃しました。私は息子が嫌なことをされたり言われたりしているのを見ると、だんだん腹がたってくる自分に気づきます。
子ども同士のことなので、口を挟むのもなんだし…と我慢していましたが、この前ついに、「なんでそんなことするの!」と爆発してしまいました。おとなげない…。
しかし、男の子なのにあまりに弱いと、小学校に入っていじめに合わないかと心配もしております。ちなみに、女の子とは気が合うようで、楽器を演奏したり楽しく遊んでいます。
いじめるほうもいじめられるほうも原因があるようですし、一概には言えないのですが、私はこれからどのようにしていけばいいのか悩んでおります。
長男は、クラスメイトにそんな態度をとられてもさほど気にもとめていないようです。発表会などで大きな声を出したりすることが得意なようで、「幼稚園は楽しい」と言います。それが救いかな?とも思いますが、少々おめでたい性格なのかもしれません。
また、主人は「成長するにつれて、友達もどんどん変わるから大丈夫だろう」というのです。本当にそうなのでしょうか。アドバイスいただけたらありがたいです。

-
- この記事に対するTrackBackのURL

-
- コメントはまだありません。
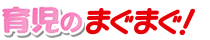




![この記事をクリップ! [clip!]](http://parts.blog.livedoor.jp/img/cmn/clip_16_16_w.gif)
























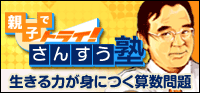
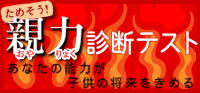

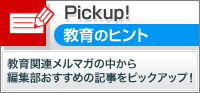
![子育て悩み相談[おしえておたくんち] 子育て悩み相談[おしえておたくんち]](http://education.mag2.com/img/common/otakunchi_miz200.gif)
![家庭でできる性教育[あなたにもできる「性と生」のおはなし] 家庭でできる性教育[あなたにもできる「性と生」のおはなし]](http://education.mag2.com/img/common/sei_miz200.gif)


